子ども相手の学校だと、先生と子どもの間には一種の権力関係があって、「教える→学ぶ」関係が前提としてある。
大人相手に教える場合は、権力関係がないので、「学ぶ」ための動機づけが必要。ではどうすればいいか、を指摘した記事です。
「大の大人」を対象にした研修では、あの手この手を使って、相手を動機付け、動かしていくスキルが求められます。単純に、「権力」によりかかるわけにはいかないのです。
情報源: 「子どもを教えること」と「大人を教えること」の違いとは何か? | 立教大学 経営学部 中原淳研究室 – 大人の学びを科学する | NAKAHARA-LAB.net
受講生を対等に扱う
子どもを相手にする場合と大人を相手にする場合の違い、それは大人の場合は相手が対等ということと記事では指摘しています。
だから。
命令形で発言するのではなく「〇〇しましょう」と促す表現で発言した方が伝わりやすい。
これはパソコン教室のような「教える→学ぶ」形態の大人向け講座であっても言えることのように思います。
相手の中から導き出す
もうひとつ、大切な指摘は、「一緒に考える」形式を重視しましょうという指摘です。
実はこれは、大人向けに限った話でもありません。子ども相手の教育でも、「アクティブ・ラーニング」形式が進んでいます。子どもたちに発見させるような学びのあり方。
なぜでしょうか。
記事の中にヒントがあります。事例となった日のテーマは必ずしも答えがある内容ではないと指摘されているところです。
答えの無い時代だからこそ
現代は、未来を見通しづらい不透明な時代です。これまでの常識が通用しないことも多い。答えのない問題が社会的に多く出てくる。
そんな時代の対処法に答えはありません。それぞれのケースごとに、自ら考えていかなくてはならない。そうした姿勢を身につけるために、アクティブ・ラーニングを経験することが欠かせない。
逆に言えば、こんな時代でも、答えのある問題に対しては、通常の教え方が効率よいでしょうね。
誰も答えを持っていない
「一緒に考える」場では、講師も自分の考えが正しいと前提することはできません。「自分はこう思うけれど、他の考え方はどうだろう」と、受講生と一緒に新しい回答を見つけていく場作りが求められる。
そのような場での講師の力量は、新しい視点を提供したり、それまでの論点を整理したりといった受講生の議論を活性化することで測られますね。
学びのあり方も、時代によって変わってきます。
▼Question for New Rules
答えの無い時代、学びの場はどうあるべきだろう?
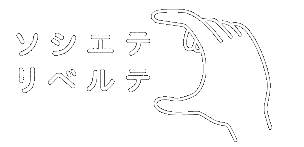
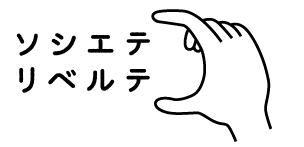

コメントはありません